防災の地域経済
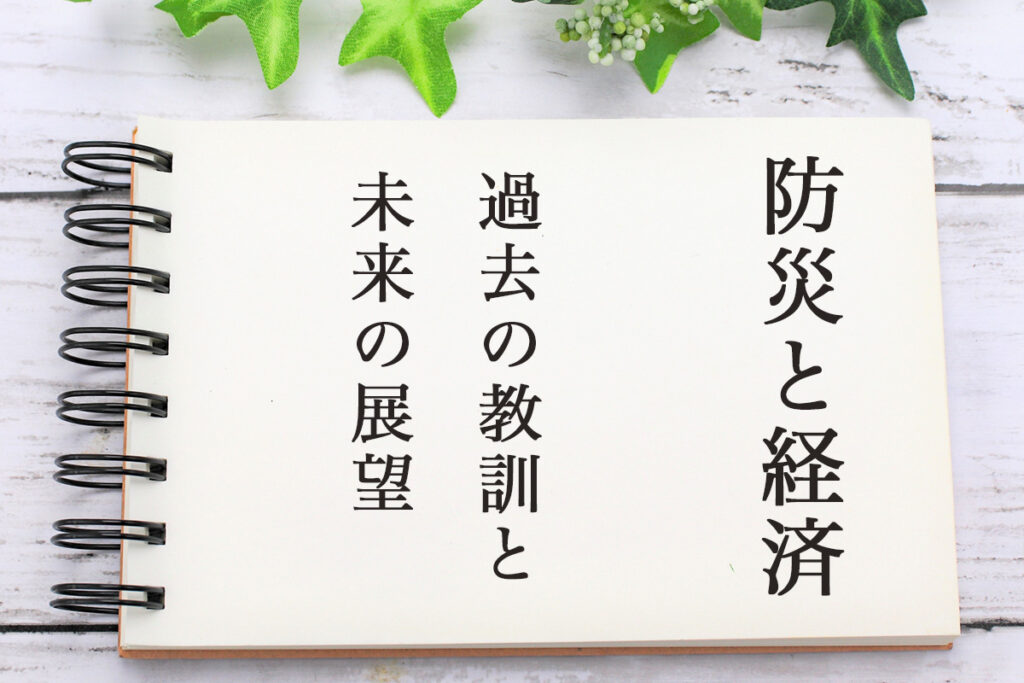
自然災害と地域経済の変遷
9月1日は「防災の日」でした。この日は1923(大正12年)年9月1日に発生した「関東大震災」に由来しています。大震災を教訓に、国民一人ひとりが災害への備えと認識を深めるため、1960年に閣議決定によって制定されました。
日本列島各地では、明治維新以降のおよそ160年だけでも多くの自然災害が発生しています。1891年には日本近代史上最大規模(M8.0)の濃尾地震が発生し、死者は7,000名以上と言われています。1896年の三陸地震津波では岩手・宮城の沿岸に津波が押し寄せ、約22,000名が死亡しています。大正時代には関東大震災が首都・東京を中心に大きな被害を与え、鹿児島の桜島では噴火による溶岩流などによって桜島が大隅半島と陸続きになりました。大阪を直撃した室戸台風では死者約3,000名に上りました。太平洋戦争中にも、東南海地震(東海地方)、三河地震(愛知)が発生しています。さらに1995年には阪神・淡路大震災が発生し、死者は約6,400名に上り、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震・津波)では死者・行方不明は約18,400名となりました。その後も熊本、北海道、能登半島で地震が発生しています。また、近年の気候変動の影響によって日本列島各地では記録的な大雨による洪水が深刻な被害を与えています。
こうした自然災害は、現代の科学的知識をもってしても発生する場所、時期そして規模を正確に予測することはできません。そのため、被害の発生を最小化するための事前の取り組みと、復興のあり方が重要になります。
明治期における自然災害からの復興は、地主や地域の共同体が主体となっており、国などの公的な支援は限定的で、義援金や寄付が大きな役割を果たしていました。関東大震災では首都を直撃したことから、復興は国家的な課題となり、帝都復興院が設置され、道路の拡幅、耐震・耐火建築の普及などのインフラ整備が進み、都市の近代化につながりました。戦後の混乱の中で発生した自然災害からの復興は、公共事業と重なって地域のインフラの近代化が促進されました。伊勢湾台風のような高度経済成長期に発生した災害においては、国土総合開発計画などよって治水事業などの防災インフラが整備され、地方の建設業や土木産業を支え、地域経済に雇用と資金をもたらす役割を果たしました。阪神・淡路大震災の際も、復興事業が都市再開発と合わさり、住宅再建・港湾機能回復に巨額の投資がありましたが、一方で中小企業や商店の倒産が相次ぎ、復興格差が問題化しました。東日本大震災では、東北沿岸部の漁業・農業・観光業が壊滅的な打撃を受けました。宅地の嵩上げ、道路整備、防潮堤の建設などの復興事業によってインフラは回復したが、地域からの人口流出や産業空洞化が深刻になっています。
一方、熊本地震、西日本豪雨、能登半島地震などの小規模自治体での災害は、人口減少地域における復興の難しさを浮き彫りにしました。さらに農業・漁業・観光などの地域産業の再建やコミュニティ維持が重要な課題となります。
このように災害復興は地域経済に対して公共投資や雇用を生み出し、地元の建設業やサービス業に対する需要が生まれます。しかしながら中長期的にみると、産業基盤の喪失、人口流出、地域経済の縮小などが課題となります。
そのため復興と同時に「まちづくり」の視点が重要になります。例えば東北では再生可能エネルギー関連の産業育成や、熊本では地震後の観光再生に取り組んでいます。復興を「復旧」だけで終わらせず、地域経済の持続的な発展に結びつけることが大切です。地震、津波、洪水、山崩れなど、自然災害の多い日本列島ですが、これからも安心・安全に暮らすために、地域の創意工夫が求められます。それぞれの地域には固有の地域資源が豊富にあります。それを活かし地域経済の復興を図り、地域の人びとが災害の伝承と防災に取り組むことが、地域経済にとって重要なのです。

お問い合わせ
ESG経営や出前授業に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームより承っております。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。


