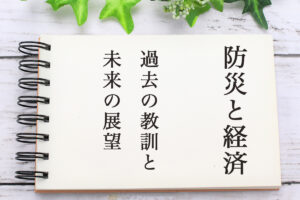アイヌの思想から

持続可能な未来を拓く自然観と暮らしの知恵
先住民族の自然環境に対する考え方に関心を持ってきました。例えば、北海道の先住民族のひとつであるアイヌ(人間という意味)民族は、北海道をアイヌ・モシリ、人間の大地と呼び、狩猟採取によって生活を営んできました。アイヌの自然観は、自然を単に人が利用するための資源としてではなく、共に生きる存在として捉えてきました。
自然はカムイ(神)の世界であり、すべての動物、植物、山、川、火、水などにもカムイとして人格を宿し、それぞれが役割を担っていると考えられています。
たとえば、ヒグマは「キムンカムイ(山の神)」として神聖な存在として崇め、重要な食料でもある鮭(さけ)は「チェプカムイ(魚の神)」としています。さらには生活に必要な道具などのモノにも魂が宿っているとするアニミズムは、日本の古来の宗教である神道にも共通するものがあります。
とくに人と動物や植物は、同じ世界に住む仲間であり、互いに姿を変えて行き来する存在であるとしています。人間は自然から恵みを受けていますが、自然に対して敬意をもち、感謝することが重要であると考えています。狩猟など自然から資源を受け取る際には、必要な分だけいただき、祈りを捧げてから採取しています。クマ送りの儀式イヨマンテなどもカムイに対する感謝のためのものです。
春になり孵化した鮭は川を下り、やがて秋になると大きく成長して海から戻ってくるカムイであり、厳しい冬の間の人の貴重な食料となり、産卵を終えると森の動物たちの生命を支える恵となります。現代風にいうならば「自然資源の循環利用」という思想にも繋がっています。
ユーカラと呼ばれる口伝えの伝承には、クマやキツネ、鮭などの自然の中で生活する動物などが人の姿で登場する話が多くあり、自然と人間が対等に交流する関係が描かれています。アイヌの言葉を聞き取ることは難しいですが、クスッと笑える話や、ちょっとした教訓もあり機会があれば触れられることをお勧めします。
現代社会は、人間が高度な文明によって大量生産、大量消費を可能にして豊かな生活を送ることができるようになりましたが、過剰な行動によって自然環境、生態系が傷つき、消費後には大量の廃棄物が発生し、ごみ問題も深刻化しています。アイヌは、必要以上の狩猟や採集をすることを避けてきました。そして春には野草や山菜を、秋には遡上する鮭やキノコや木の実を大切に採取するように季節ごとに利用する資源を変えることで自然の再生を促すことのできる思想は、持続可能な社会にとって大切な知恵となるのではないかと思います。
わたしたちの住んでいる北海道には、まだ豊かな自然環境が残されています。こうした自然環境は私たち人とともに社会にとっても重要な資源として子どもや孫の世代に大切に継承していく必要があります。こうしたアイヌの自然に対する思想を現代の環境保全に対する取り組みやエコツーリズムに応用することができるのではないでしょうか。そこには新たなビジネスの種(シーズ)も隠されています。現代に生きるわたしたちは、アイヌの自然との共生に対する思想から学べることが多いのではないでしょうか。

お問い合わせ
ESG経営や出前授業に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームより承っております。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。