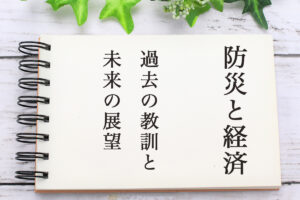自然の恵みに感謝して

ハロウィンから新嘗祭まで、食と文化のつながり
今年のハロウィンは10月31日(金)です。ハロウィンといえば、カボチャや魔女などの仮装イベント、一部の若者による羽目を外した行為などを連想しますが、世界的なイベントであるハロウィンの起源をたどると、古代ケルト人の「サウィン(Samhain)」という儀式が始まりとされています。
ケルト民族にとって、秋が深まる10月31日は一年の終わりでした。この夜は現世と来世の境界が曖昧となり、先祖の霊が戻ってくると信じられていました。同時に、悪魔や魔女などの悪霊も現れると考えられ、人々は仮装をして悪霊から身を守ったといわれています。
言い伝えによれば、ジャックという男が生前に悪行を重ねたため、死後に天国へ行くこともできず、さらに悪魔をもだまして地獄にも堕ちませんでした。彼は悪魔からもらった火をカボチャをくり抜いたランタンに灯し、闇夜をさまよったとされます。これが「ジャック・オー・ランタン」の由来であり、ランタンを灯す習慣につながったといわれています。また、この日は収穫を祝う意味もあり、アイルランドからの移民によってアメリカに伝わり、世界中に広まった行事となりました。
ところで、感謝祭は「サンクスギビングデー(Thanksgiving Day)」と呼ばれ、アメリカやカナダでは祝日のひとつとなっています。アメリカでは毎年11月の第4木曜日、カナダでは毎年10月の第2月曜日に行われます。
アメリカの感謝祭は、イギリスからマサチューセッツ州プリマスに移住したピルグリム・ファーザーズが収穫を祝った行事が起源とされています。1620年、ピルグリムがプリマスに到着した年は寒さが厳しく、作物も収穫できず、多くの人びとが亡くなりました。翌年、近隣に住んでいた先住民ワンパノアグ族がトウモロコシなどの栽培方法を教え、その秋には豊作となりました。そこで、ピルグリム・ファーザーズはワンパノアグ族の人びとを招き、神の恵みに感謝して共にご馳走を分かち合ったのが始まりとされています。
さて、我が国にも「新嘗祭(にいなめさい)」という行事があります。これは天皇が新たに収穫されたお米を神様にお供えし、国民の幸せを祈る重要な宮中祭祀のひとつで、1300年以上続いている伝統行事です。新嘗祭が行われる11月23日は「勤労感謝の日」として国民の祝日にもなっています。
2023年度の日本における食料自給率は、カロリーベースで38%、生産額ベースで63%と、長期的に低下傾向にあります。温暖化などの気候変動、相次ぐ気象災害や鳥獣による食害に加え、農業従事者の高齢化による担い手不足によって、日本の農業は一層厳しさを増しています。そのなかで最も重要なのは、農家の安定した経営基盤を確立し、自給率を高めることです。
地域経済における農業の役割は、食料供給だけにとどまりません。障害者や高齢者の雇用創出、観光誘客、環境保全など多岐にわたります。また、農業と地域の多様な事業者が連携し、新たな商品開発や付加価値の創造を進めることで、魅力的な地域コンテンツを発信し、農業を核とした地域活性化が期待されます。
そのことを心に留め、農家の方々と自然の恵みに感謝しながら、秋の味覚をいただきましょう。

お問い合わせ
ESG経営や出前授業に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームより承っております。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。