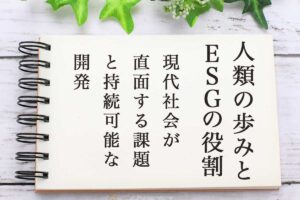「三方よし」と「三」の持つ絶妙なバランスとは?

「三方よし」をご存知でしょうか。
これは、江戸時代に各地を行商していた近江商人の商売のコンセプトです。現代の大手商社の一つも企業理念として掲げています。
商売とは、売り手が商品を販売して利潤を得ることが基本ですが、質が良く適正な価格で売れば、買い手も商品やサービスを購入して満足することができます。このように、売り手と買い手の双方に加えて、「三方よし」の三方の一角は「世間」であるとされています。世間は、現代風に言えば「社会」と言い換えることができるでしょう。市場を通じて企業と消費者が商品やサービスを売買し、経済学では「効用」とされる満足度をそれぞれが最大化するだけでなく、社会全体も豊かにならなければならないという考え方です。これは、原材料の選択、商品の作り手や製造方法をはじめ、消費後の廃棄物が環境に与える影響にまで配慮することではないかと思います。
さて、この「三」という数字は、とてもバランスが取れています。
アメリカのかつての宇宙計画であるアポロ計画では、人類が月面を目指し、狭い宇宙船の中に三人の宇宙飛行士が乗り込んでいました。漆黒の宇宙空間を一人で旅するのは孤独ですし、緊急事態に遭遇した際に冷静で適切な行動を取ることが難しくなる恐れがあります。二人だと意見が対立した場合に収拾がつかなくなる可能性もあります。しかし、三人であれば、対立する二人を仲裁することもできます。宇宙船に搭載できる資材や飛行士の重量には制限があるため、多くの飛行士を乗せることはできません。こうした理由から、三人という人数が決定されたのではないでしょうか。
また、古代中国には青銅製の鼎(かなえ)という容器があります。鼎は、調理や宗教儀式に使われた器とされていますが、鍋型の胴体には三本の足がついており、微妙なバランスで作られています。一本足や二本足では自立することが難しいのですが、三本足で支えると絶妙な安定感が生まれます。
さらに、古典落語の「三方一両損」という演目にも、「三」という数字が登場します。
三両入った財布を拾った左官の金太郎は、それを落としたのが大工の吉五郎であるとわかり、返そうとします。しかし、江戸っ子の吉五郎は、男気として「落とした金は受け取らない」と言い張ります。一方の金太郎も、「この金は確かにあんたのものだ」と譲りません。そこで仲裁に入った江戸町奉行の大岡越前は、自らの一両を加え、正直に届けた金太郎に二両、落とした吉五郎にも二両を渡し、それぞれが一両ずつ損をした形にして納得させました。こうして「大岡裁き」によって一件落着した後、二人にお膳が振る舞われます。大食いの二人に対し、大岡越前が注意すると、二人は「多く(おおおか)は食わねえ」「たった一膳(えちぜん)」と洒落を交えて答えた、というお話です。
現代社会においても、企業や消費者は過度な利益追求や浪費を避け、少しだけ我慢をすることが求められている――そんな江戸時代の先達からの忠告のようにも聞こえます。

お問い合わせ
ESG経営や出前授業に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームより承っております。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。